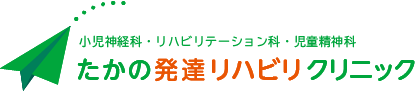
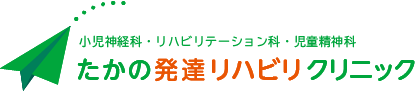

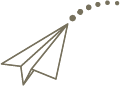
No.33
発達障害治療介入におけるエビデンスとは
昨年このブログで「ポリヴェーガル理論」や「原始反射」について、エビデンス、エビデンスと言っていましたが、いまは、「Evidence-Based Medicine」(エビデンス・ベースド・メディスン、EBM)の時代です。
EBMは日本語では、「(科学的)根拠に基づいた医療」と言われ、科学的に正しいと証明された根拠のある医療行為(診断や治療など)ということです。EBMに基づき、多くのガイドラインが作成され、今ではメジャーな疾患については、ほとんどすべてガイドラインが存在しています。
例えば、糖尿病の人がやってきた、あるいは、細菌感染が全身にまわりショック状態となった人が救急搬送されてきたとき、どういう検査や、治療をするかは、決められています。ガイドラインに従い、どこの施設でも大差ない標準的な医療行為が行われます、というか行われなければなりません。これが、EBMです。
では、自閉スペクトラム症(ASD)や注意欠如多動症(ADHD)など神経発達症(発達障害)のこどもが来院したとき、我々はどうすべきでしょうか。医療機関としてはエビデンスのある介入をしなければなりません。
糖尿病に勝手な治療をしてはいけないように、発達障害に対しても、医療機関で保険診療を行っているからには、エビデンスのある治療を提供しなければいけないのです。
「ポリヴェーガル理論」や「原始反射が発達障害の困りごとの原因」というような言説に対して、エビデンスがない、似非科学とえらそうに言っていた私は何をしているのだという話です。
発達障害、とくにASDへの支援、介入方法として、TEACCH(Treatment and Education of Autistic and related Communication handicapped Children、ティーチ)、ABA(Applied Behavior Analysis、応用行動分析)、PECS(Picture Exchange Communication System、ぺクス、絵カード交換式コミュニケーションシステム)、PCIT(Parent-Child Interaction Therapy、親子相互交流療法)、CARE(Child-Adult Relationship Enhancement)、感覚統合療法(Sensory Integration Therapy)などが知られています。
私も名前だけは聞いたことがあるけど、具体的な内容は知らないものも多いのですが、その中でもとくに、有効とされるものに、ABA(応用行動分析)による介入があります。
応用行動分析は以前にもここでふれたことがありますが、社会的に重要な人間の行動を分析し、その分析に基づき、外的条件を変化させることによって人間の行動を変え、社会を変えようというものです。
応用行動分析では、行動の原因をその人の性格や能力というような個人の内的要因には求めません。
行動を個人の内的要因としてとらえる考えは、結局、個人の資質が問題ということになり、何も行動は変えられないということになります。
変えようがない個人の能力や性格を変えようとしてもそれは無理なことであり、結局何も変化は起こらないわけです。
応用行動分析では、行動は、外的環境との関わりで引き起こされるものであり、その行動の制御要因は外部にあると考えます。したがって、外部の要因を分析し、環境を変えることにより、行動を変えられると考え、行動を変容していきます。
実際の療育では、行動の前後を観察し、その行動を引き起こしたのは何なのか、その行動を起こして結果どうなったのかを明らかにします。これらの観察・分析から、望ましい行動を増やし、好ましくない行動を減らします。望ましい行動を増やす強化子や好ましくない行動を減らす弱化子を見つけそれらを利用していきます。
具体的に、ABAを利用した療育方法としては、DTT(Discrete Trial Training、離散試行型指導法)、PRT(Pivotal Response Treatment、機軸反応支援法)、ESDM(Early Start Dener Model、早期支援デンバーモデル)、JASPER(Joint Attention Symbolic Play Engagement Regulation、共同注意・象徴遊び・関わり合い・感情調整)などがあります。
ABAによる療育の有効性についての報告はLovaasの1987年の論文が最初とされています。2-3歳の自閉症児を対象にABAに基づく介入を行ったところ、介入群では通常療育群より、4年後のIQが30以上高かったという驚くべき結果が得られました。少数例の報告ではありますが、衝撃的なものでした。
ただし、この報告では、週平均40時間のトレーニングを2年以上行っています。つまり1日6時間程度のトレーニングを毎日、2年間行っているわけです。
ABAに関わらず、これだけの量、濃密なトレーニングを行えば、良い結果は出そうにも思いますが、その後も、DTT、PRT、ESDM、JASPERなど、ABAを利用したトレーニングの有効性は次々と報告されました。その対象となったのは、1歳半から4歳、とくに2-3歳までの知的障害を伴ったASD児です。つまり、知的障害を伴うASDでは、早期(3歳まで)からABAを利用したトレーニングを行うべきというエビデンスが形成されたわけです。
DTTは日本語では、不連続試行訓練とか離散試行型支援法とか呼ばれていますが、日本語の意味としても何のことかよくわかりませんよね。英語のdiscreteは、「個別の」とか「分離された」と言う意味で、不連続というより、一つ一つの行動を細かく分離して、一つ一つ区切ってトレーニングするという意味です。
例えば、「スプーンを使って食事をする」という行為について考えてみますと、簡単な一つの行動のように見えますが、それは、「椅子を引く」「椅子に座る」「テーブルと椅子を適当な位置に保つ」「姿勢を正す」「スプーンを持つ」・・・・という一つ一つの小さな行動の集合なわけです。それぞれ、一つ一つの行動を分離して、それら一つ一つの行動を強化子を用いて条件づけるというトレーニングを行うわけです。
「椅子に座って」と指示して、実際に椅子に座るという行動ができれば、褒めて、お菓子をあげるなどの強化子を与えるということをします。これを繰り返していき、お菓子をあげるというような強化子なしでも、褒めてあげる、笑顔を返すというようなことだけで、その動作ができるようにします。
もちろん、全てがそううまくいくわけでなく、急に泣き出したり、椅子を倒したりなどのイレギュラーなことが起こることもあるわけです。それに関しては、ABAの考えから、何がその行動を引き起こしたかを分析し、望ましい環境調整が必要かもしれませんし、望ましくない行動を弱化する因子も利用しないといけない場合もあるかもしれません。
DTTはこのように、ドリル学習のようなことを行うものです。
一方それ以外に、もっと自然な形での日常生活の中でのかかわりを利用した方法もあります。これはNaturalistic Developmental Behavioral Interventions(自然主義的発達行動介入、NDBI)と呼ばれ、PRT、ESDM、JASPERはNDBIにあたるものです。
こどもが日常生活の中で学習できるように、生活場面の流れの中で自然な形の介入を行うとされています。私も具体的にどのような形でどのように行うのかはよく知らないのですが、日常生活の中での介入ということになりますので、保護者が行う日々の生活の中での介入が重要になってきます。そのために保護者への指導も必要です。
ただ、こどもをよく見ておられるお母さん(お父さんもですが)は、自然にABAの視点を利用した子育てをされているのではないかと思います。それをもう少し体系的に行うということです。
以上のように、少なくとも知的障害を伴うASDでは、ABAを利用した介入が有効であることが示されています。
とくに、2-3歳までの早期介入の効果は高いと言われています。これが、EBMに基づく治療介入です。ところで、現在、我が国では、そのような体制ができているかと言われると、ほとんどできていないというのが実情だと思います。
入学試験の季節です。高校入試、専門学校入試、大学入試、もう終わった方もおられると思いますが、もう目の前にあとひと頑張りという方もおられると思います。
頑張れ!
岡村孝子 「夢をあきらめないで」OFFICIAL MUSIC VIDEO
著者 たかの発達リハビリクリニック
院長 高野 真
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前診 9:00~12:00 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 午後診 13:30~ 18:00 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
休診日:水曜、日曜、祝日 |
 |
〒655-0004神戸市垂水区学が丘7-1-33東多聞台クリニックビレッジ
Copyright (C) 垂水区 小児神経科・リハビリテーション科・児童精神科 たかの発達リハビリクリニック. All Rights Reserved.