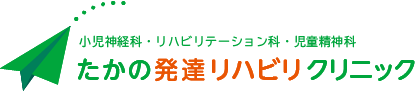
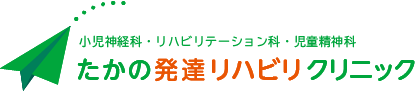

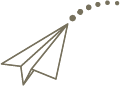
No.20
精神科や心理学的治療の一つに、「行動療法」という治療法があります。現在では、精神科領域の治療に関わらず、医学全般の教育的指導や犯罪者の矯正、一般の意識や行動の変容にも応用されています。
別に行動療法が何であるのかを一般の人は知る必要もないかもしれませんが、私自身わかったような、わからないようなところがあり、自分自身の整理のためにも「行動療法」について考えてみたいと思います。
精神科では、薬物療法とともにというか、それ以上に大切なものとして、心理的な治療が行われます。
いわゆる心理的な治療、狭い意味での「心理療法」というのは、何をどう感じて、どう考えているのか、原因はどこにあるのか、本人の意識しない無意識のこころの中や幼少期の経験の中に真の何か原因があるのではないか等を突き詰め、こころの問題としてそれを解決しようとする治療法です。
一方、行動療法は、とりあえず、原因やこころの問題はおいておき、行動を改善するということを焦点に、目的とする行動、望ましい行動ができるように練習するという治療法です。
「行動療法」をwikipediaでみてみると、「行動療法とは、心理療法のひとつで、学習理論(行動理論)を基礎とする数多くの行動変容技法の総称。近年は広義の認知療法との交流・統合が進展し、認知行動療法と称されることも多い。行動療法においてターゲットとすべきは客観的に測定可能な「行動」であり、また目標とすべきは望ましくない行動の「強化」や「弱化」といった行動の制御である」とありますが、まったく何のことかわかりません。
もう少しネットで、「行動療法」について調べてみると、「レスポンデント条件づけ」と「オペラント条件づけ」が基本的手法であると出てきます。 さらに何かわかりませんよね。「レスポンデント条件づけ」とは古典的条件づけとも呼ばれ、有名な例はパブロフの犬です。
エサを与えるときに同時にベルを鳴らすということをしていると、ベルを鳴らすだけで、エサがなくても、犬はよだれを垂らすようになるというものです。ベルを鳴らすということで、よだれを垂らすという行動が条件づけられたわけです。
「オペラント条件づけ」は、ネズミをケージに入れ、レバーを押すとエサが出てくるようにしておくと、ネズミはそれを学習して、レバーを押すようになります。レバーを押すという行動が条件づけられたわけです。
これが、人間の治療に何が関係するのという感じですが、要は、「エサ(報酬)を目的に新しい行動を覚えた(学習した)。報酬があれば、その行動をすすんでする」というのが私の理解です。逆に、例えば、レバーを押せば電気が流れたりすると、レバーを押さなくなるので、「罰(ペナルティー)があれば、その行動はしなくなる」ということです。
これを人間の治療や行動変容に利用しようというのは、誰でも思いつくと言えば思いつくことですし、大きな勘違いと言えば、大きな勘違いだと思います。
そこで、さらに調べてみますと(すべてネット情報程度ですが)、「行動療法」の代表的なものとして、ABA(応用行動分析学)の利用というのがでてきます。ABA(応用行動分析学)とは、多くの人間の行動を分析することによって、そこに共通する法則を見出し、その法則を利用して、人間の行動をコントロールしようという学問だそうです。
その実際のやり方として有名なものに、ABC分析があります。行動療法の目的は、望ましい行動を増やし、望ましくない行動を減らすことでしたが、言い換えると、望ましい行動を強化し、望ましくない行動を弱化することです。ある行動を強化する要因を強化子、弱化するものを弱化子と呼びます。ABC分析では、その行動が、何によって強化(あるいは、弱化)されているのかということに着目します。つまり、行動の強化子(弱化子)を見つけることに焦点を絞り、行動の前後を含め3つの要素に分けて分析します。
それは、「A(Antecedents):先行事象、B(Behavior):行動、C:Consequence:結果」です。
「○○のときに(A)、○○したら(B)、○○になった(C)」このことから、強化子を見出し、その強化子を利用して、望ましい行動を増やそうというものです。
よくあげられる例に、次のようなものがあります。こどもと一緒にスーパーに買い物に行ったら、お菓子売り場でほしいお菓子がありました。そこで、その子は、「お菓子がほしい」と泣きわめき、母親は仕方なくそのお菓子を買い与えました。
これを、ABC分析に当てはめると、A:一緒に買い物にいって、お菓子売り場を通りがかりほしいお菓子を見つけた。B:お菓子を買ってもらうために大声で泣きわめく。C:お菓子を買ってもらえる。となります。そこでABC分析では、「お菓子を買ってもらえる」ということが、「大声で泣く」という望ましくない行動の強化因子となっているということになります。
さらに、何があってもお菓子を買わなければ、期待した結果が得られないわけで、大声で泣くという望ましくない行動は弱化されるというような説明がなされています。 しかし、普通に考えて、物事はそんなに単純ではないです。
何でもかんでも要求が通るのはよくないとは思いますが、要求が満たされずに終わることは本当にいいことなのか?泣くことは悪いことなのか?それで要求が満たされることは常に悪い強化因子となっているのか?等いろいろなことを考えます。また、現実場面での対応をどうするかも非常にむずかしい問題があります。
ABAでABCすれば問題は解決だ、とは誰もがすぐには思わないと思います。
ただ、行動の強化、弱化というのは意外なことにあったりするかもしれないので、こういう視点は参考になると思います。
また、先行事象に目を向けることも有用だと思います。
一緒に買い物に行った、お菓子売り場を通りかかった、また、ひょっとしたら、お腹がすいているとか、とくに昨日今日、友達がおいしそうなお菓子を持っていたとかいうような条件もあるかもしれません。先行事象に問題はなかったか、行動の強化因子、弱化因子は何か、単純に行動の強化、弱化と考えていいのか、こういう分析をすることはいろいろな視点を与えてくれます。普段の生活をふりかえる、考えてみるという意味では、適度にこういうことをやってみるのはいいと思いますが、家庭生活でいちいちこんなこと考えて行動していたら、何にもできません。療育や教育を本業でやる人に任せておくのがいいかもしれません。
というようなところで、私が「行動療法」について思うことを述べてみます。
「人は、悲しいから泣くのではなく、泣くから悲しくなである」ということを聞かれたことがあるかもしれません。逆説的な話なのですが、悲しいというのは脳(中枢)が感じるのが最初ではなく、起こった変化や動作(末梢)から脳が感じるのだということで、これは「感情の末梢起源説」と呼ばれています。
泣いていると悲しくなるのは事実ですし、それが悲しいということだと学習してきた影響はすごく大きいと思います。でも、最初の涙は悲しいから出てくるんじゃないのという疑問はありますが、少なくとも人間の感情は、自分の体に生じた変化や動作・行動に大きく影響を受けているのは事実だと思います。
似たような感情の影響の受けやすさを示すものに、「つり橋効果」という現象があります。
高いところのつり橋を渡る時、人は怖くてドキドキしますが、それを異性の知人と一緒に渡った場合、恐怖によるドキドキを一緒に渡っている人へのときめきのドキドキと間違って認識してしまうというものです。
また、「単純接触効果」と呼ばれる現象もあります。これは、同じものや人に接する回数が増えていくと、徐々にその対象に良い印象をもつという現象です。それほど好きでもない人の写真を貼っておき、毎日眺めていると、だんだんその人のことが好きになっていくというようなものです。
このように、自分の中で自然にわき上がってくる、あるいは、自分が形作っていると思っている感情も、実は環境や行動に大きく規定されているのです。したがって、行動を変えることにより、感情パターンや思考パターンを変えることができるわけです。
まあ、毎日、夫(妻)の顔を見ていると、ますますイライラしてきますという意見もおありかもしれませんが、それは心理学者に文句を言ってください。私も徳島県の祖谷にあるかずら橋を妻と一緒に渡ったことがありますが、すごく怖かったので、心臓がドキドキしましたが、これは、下手したら妻を突き落としてしまうのではないかというドキドキかもしれないとわからなくなりました(ウソですよ)。
したがって、私の思う「行動療法」は、何らかの行動を起こすことが重要である。それが目的とする行動の擬似行動であれば、目的行動と勘違いする、心理的に目的行動が受け入れやすくなるというものです。
直接的に目的とする行動を行おうとする場合は、まずはそれを受け入れられる心の準備が重要なので、環境の調整やイメージトレーニングのようなものが必要です。その受け入れの意味でも、擬似行動から開始するのがいいと思います。
最初は、似ているとは言えるのかよくわからない遠く離れた行動でもいいと思います。極端に言えば、意味のない行動でもいいと思います。ただ継続すること少しずつステップアップすることが重要ですので、何らかの本人の満足、達成感が得られる行動であるのが望ましいのは当然です。
先にも述べましたが、これまでの行動療法は、何々療法、何々療法とかいろいろ言われていますが、せんじ詰めれば、結局のところ、何らかの物質的なご褒美(トークンエコノミー)と罰(ペナルティー)で行動を強化するか、弱化するかだけだったと思います。やはり、一番重要なのは、本人を満たしてくれる気持ちややりがい、充足感だと思います。もちろん、そこが一番むずかしいところなのですが。
もちろん、「行動療法」にも当然弱点や限界があります。行動だけに焦点を絞って、本当に問題が解決されるのか、背後にある要因や心理的な問題の解決なしでは真の解決には至らない、という問題は当然ながらあります。
その意味で、「行動療法」も「先行事象」に目を向け、その要因を考える方向へと発展していきました。このようなことから、最近では、「認知療法」と「行動療法」とを合わせた形の「認知行動療法」の有効性が報告され、いわゆるエビデンスのある治療として推奨されています。
今回は、「認知行動療法」の詳細には触れませんが、「認知」の偏りや歪みからくる行動を振り返り、「認知」の問題を修正していく方法です。ただ、私にはこれは行動療法的ではなく、認知療法の一環のように思います。
行動に働きかけ、行動を変えることによって、物事の捉え方や考え方、そして、その人の感情が変わっていくところが、「行動療法」のいいところであり、「行動療法」は有効性だと考えます。
やさしくかわいく イラつかず
すごいぞ私
ママさん、パパさん子育て大変だと思いますが、頑張ってください。
著者 たかの発達リハビリクリニック
院長 高野 真
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前診 9:00~12:00 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 午後診 13:30~ 18:00 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
休診日:水曜、日曜、祝日 |
 |
〒655-0004神戸市垂水区学が丘7-1-33東多聞台クリニックビレッジ
Copyright (C) 垂水区 小児神経科・リハビリテーション科・児童精神科 たかの発達リハビリクリニック. All Rights Reserved.